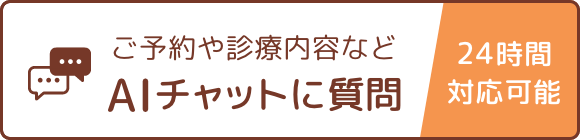歯科
歯科診療のご案内

「最近、愛犬・愛猫の口臭が気になる…」 「歯が黄色く、汚れてきた気がする…」
そう感じたことはありませんか? 私たち人間が毎日歯を磨くように、ワンちゃん・ネコちゃんにもお口のケアが不可欠です。しかし、彼らは「歯が痛い」や「口の中に違和感がある」と私たちに言葉で訴えることができません。
お口の健康は、全身の健康を守るための第一歩です。 大切なご家族がいつまでも元気に、おいしくご飯を食べられるように、私たちがサポートします。
3歳以上の約8割が「歯周病」
実は、3歳以上の犬・猫の約8割が歯周病であると言われています。
歯周病は、歯の表面に付着した「歯垢(プラーク)」の中の細菌によって、歯茎(歯肉)や歯を支える骨(歯槽骨)が炎症を起こし、徐々に破壊されていく病気です。
歯垢は、わずか3~5日で歯磨きでは取れない硬い「歯石(しせき)」に変わってしまいます。
歯周病を放置するとどうなるの?
歯周病は、お口の中だけの問題にとどまりません。
- 強い痛みと不快感 歯茎が腫れ、出血し、痛みが出ます。硬いフードを食べたがらなくなったり、食欲が落ちたりすることがあります。
- 歯が抜ける・顎の骨が折れる 歯を支える骨が溶け、歯がグラグラになって最終的に抜け落ちてしまいます。重症化すると、顎の骨がもろくなり、くしゃみなどで骨折してしまうこともあります。
- 全身の病気へのリスク 歯周病菌が血管を通って全身に広がり、心臓病、腎臓病、肝臓病といった命に関わる病気を引き起こす(または悪化させる)可能性があります。
こんなサインはありませんか? ~お口のSOS~
以下の項目にひとつでも当てはまったら、早めの受診をおすすめします。
- 口臭が強くなった(一番気づきやすいサインです)
- 歯が黄色や茶色になっている(歯石の付着)
- 歯茎が赤い、または腫れている
- よだれが多い(血が混じっていることもある)
- 硬いものを食べたがらない、食べこぼす
- 片方の歯だけで噛んでいるように見える
- 口元を触られるのを嫌がるようになった
- くしゃみや鼻水が増えた(歯の根っこの炎症が鼻に影響することがあります)
当院の歯科診療
1. 歯科検診・口腔内チェック
まずは視診や触診で、歯石の付着具合、歯茎の炎症、歯のぐらつきなどを丁寧にチェックします。ワクチン接種や健康診断の際にも、お気軽にお口のご相談ください。
2. 精密検査(歯科レントゲン)
歯周病の本当の怖さは、歯茎に隠れた「歯の根っこ」や「歯を支える骨」で進行することです。当院では歯科専用のレントゲンを使用し、目に見えない部分の病気(歯周ポケットの深さ、骨の溶け具合、歯の根の先の炎症など)を正確に診断します。歯科レントゲンには鎮静もしくは麻酔が必要になります。


3. 全身麻酔下での安全な歯科処置
当院の歯科処置は、安全と確実性のために、必ず全身麻酔をかけて行います。
なぜ全身麻酔が必要なの?
- 痛みと恐怖を与えないため 動物は口を大きく開けたり、器具を使われたりすることに強い恐怖を感じます。麻酔なしでは、そのストレスや痛みで処置がトラウマになってしまいます。
- 「見えない部分」を徹底的に治療するため 歯周病の原因は、歯と歯茎の隙間(歯周ポケット)に隠れた歯石や細菌です。無麻酔で表面の歯石を取るだけでは、根本的な治療にならず、病気は進行してしまいます。
- 誤嚥(ごえん)を防ぐため 処置中に出る水や、除去した歯石・細菌の塊が気管に入ると、重い肺炎(誤嚥性肺炎)を引き起こす危険があります。全身麻酔下では、気管にチューブを入れて気道を確保するため、安全に処置が行えます。
※麻酔前には必ず血液検査や胸部レントゲン検査などを行い、獣医師が全身状態をしっかり評価した上で、その子に最適な麻酔プランを選択します。
主な歯科処置の流れ
術前検査:午前中に来院していただき術前検査を行います。高齢の子や、基礎疾患がある子は1週間ほど前に検査をしておきます。
麻酔導入:検査に異常がなければ12時から13時ごろに全身麻酔をかけます。

歯の評価:歯科処置の前に口腔内の写真撮影と歯科用レントゲンでそれぞれの歯の評価を行います。

スケーリング(歯石除去) 超音波スケーラーという専用の機器を使い、歯の表面と歯周ポケットの内部にこびりついた歯石を、水の振動で細かく砕きながら徹底的に除去します。当院では専用の拡大鏡を用いて処置を行います。

ポリッシング(研磨) 歯石除去後の歯の表面は、目に見えない細かな傷がついています。そのままだと再び歯垢が付きやすくなるため、専用の研磨剤(ペースト)で表面をツルツルに磨き上げ、汚れの再付着を防ぎます。

抜歯(必要な場合) 歯周病が重度でグラグラになっている歯や、折れて根っこだけになった歯は、痛みの原因となり、周囲の健康な歯にも悪影響を与えます。診断の上、必要と判断された場合は、抜歯処置を行います。
縫合:抜歯があった場合、炎症を引き起こしている歯肉を切除し歯肉の粘膜を縫合します、犬歯などの大きい歯の抜歯時は、口鼻空瘻(口腔と鼻腔をつなぐ瘻管)になってしまわないようにフラップを作成して縫合します。

治療よりも大切な「予防」
歯科治療でお口がきれいになっても、毎日のケアを怠れば、また歯垢・歯石が付着してしまいます。 お口の健康を維持するために最も重要なのは、お家でのセルフケアです。
最も効果的な予防法は、歯ブラシを使った歯磨きです。 歯垢が歯石に変わる前に、ブラッシングで物理的に取り除くことが理想です。しかし、いきなり歯ブラシを口に入れると嫌がってしまう子がほとんどです。
歯磨きステップアップ法
- 口の周りや歯茎を指で優しく触ることに慣れさせます。(ご褒美をあげながら)
- 指に歯磨きシートやガーゼを巻き、歯の表面を優しくこすってみます。
- 動物用の美味しい歯磨きペーストを指につけて舐めさせ、味に慣れさせます。
- 指サックブラシや歯ブラシにペーストをつけ、まずは前歯から挑戦。少しずつ奥歯も磨けるようにしていきます。
大切なのは、「嫌がる前にやめること」「毎日少しでも続けること」です。
歯磨きが難しい場合でも、デンタルガム、デンタルおもちゃ、飲み水に混ぜるケア用品など、様々な補助的ケアがあります。
当院では、その子の性格やライフスタイルに合わせた最適なホームケアの方法を、獣医師や愛玩動物看護師が一緒に考え、アドバイスさせていただきます。 「どうやって始めたらいいかわからない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
主な歯科の疾患
根尖膿瘍
歯周病菌が歯髄に感染し、歯の根っこの部分(歯根部)に膿がたまる病気です。悪化すると顔が腫れたり、皮膚に穴が開くことがあります。
猫の歯肉口内炎
「難治性口内炎」とも呼ばれ、猫に特有で、治療が非常に難しい口腔内の炎症性疾患です。歯に付着した歯垢(細菌)や猫カリシウイルス(FCV)、猫免疫不全ウイルス(FIV)、猫白血病ウイルス(FeLVウイルス)などに対する過剰な免疫反応により、口腔内の組織を攻撃してしまう病態。強い痛みと食欲不振を引き起こすことがあるので全顎抜歯が必要になることもあります。
吸収病巣
主に猫に見られる病気で、歯の組織が体によって溶かされていく病変です。非常に痛みを伴います。多くの場合は抜歯が必要です。

歯の破折
硬いおもちゃやおやつを噛んだり、事故などで歯が割れたり欠けたりする外傷です。神経(歯髄)が露出すると強い痛みを伴い、細菌感染から歯髄炎や根尖膿瘍に進むことがあります。抜歯やレジンによる歯冠修復が必要になります。

獣医師からのメッセージ
お口の健康は、ご家族のQOL(生活の質)に直結します。 痛みがなく、自分の歯でおいしくご飯を食べられることは、動物たちにとって大きな幸せです。また近年、歯周病菌は心臓病や腎臓病など多くの全身性の病気の引き金になるともいわれています。毎日歯磨きを頑張ってはいても、人と同じレベルで歯磨きをできる子は数少ないです。だからこそ、犬猫は人以上に麻酔下での歯科処置が必要になってきます。「口臭は当たり前」「年だから仕方ない」と諦めず、まずは一度、お口のチェックにいらしてください。